7月29日に夏の甲子園出場校49校が出揃いました。
昨夏の決勝進出チームである京都国際と関東一、今春のセンバツ優勝、準優勝の横浜と智辯和歌山など例年以上に実力校が多く揃った印象です。
しかし、そういった実力があるチームも予選では厳しい戦いを経験。
全国大会ほど脚光を浴びることはないといえ、各都道県予選にも大きなドラマがあることは確かです。
今回ご紹介するのは前回反響の高かった記事「【大幅減】夏の高校野球 地方大会(予選)の参加校数推移をまとめました!」の延長で、予選参加校を地区別にまとめたものになります。都道府県単位の推移と概ね比例しますが、あらためてマクロの視点でもご覧ください。
地区別の推移を探る
まずは結論から!
以下、地区別の推移をまとめた表になります。

やはり、北海道と東北の減少率が目立ちますね。
北海道は来年の夏から支部予選が廃止され、他府県と同じようにトーナメント形式の予選に変更されることが既に発表されています。
移動の負担増などが懸念されていますが、参加チーム数にどれぐらいの影響が出るか。
また、今年北北海道の予選に参加したチーム数は「71」。
南北海道よりも減少のペースが早く、このまま減少が進むと北海道の二代表制に異議を唱える声が上がるのも時間の問題かもしれません。
東北も厳しいですね。
6県全てで減少がとまらず、2010年は全体で420チームが予選に参加していましたが、今年ついに200チーム台に突入しています。
全国的に見て最も減少が緩やかのは東海地区。
減少率の低さでいえば4県全てが全国上位15位以内にとどまっている点が大きく影響していると言えます。
全国合計のチーム数は?
地区別のチーム数がわかったところで、さらに全国合計のチーム数も見て、マクロレベルをさらに上げてみます。

この15年で全国的に15%の減少率、600チーム以上が大会から姿を消したことがわかります。
1都道県単位にならすと約13チームの減少。
このように考えると結構大きな減少数ですね。
人口減少や高齢化により、15年後の2040年はさらに参加チーム数は減るでしょうか。
仮に次の15年(2025年-2040年)も15%減とすると、チーム数は2800程度になります。
野球離れの要因は諸々ありますが、1都道府県1代表の重みが薄れ、今後かつての予選方式(京都滋賀で1代表、奈良和歌山で1代表のような方式)に逆流していく可能性も捨てきれません。
センバツ出場枠の見直しについて

冒頭で貼付した表を再掲しますが、こう見るとセンバツの出場枠について疑問を感じる高校野球ファンも一定数いるのではないでしょうか。
現行の出場32校の内訳は
北海道1、東北3、関東5.5、東京1.5、北信越2、東海3、近畿6、中国2、四国2、九州4
で、これに21世紀の2枠が加わります。
単純に参加チーム数の比較で言えば、近畿が優遇されていることは明白で、
関東・東京地区に1枠を譲っても良いような気もします。
冷静に見れば、6府県の近畿と8県の九州がほぼ同数であることもわかります。
(筆者は近畿出身、近畿在住のため現行のほうが嬉しいですが)
他にも四国の倍近いチーム数を誇る中国と北信越が同じ2枠にとどまるなど不平等感をあげたらきりがないかもしれませんが、このようなデータを基に議論を生み出していくことも今後の高校野球を考えるうえで大切だと思います。
2022年のセンバツでは東海地区の選考が物議を醸し、大きな話題になりました。
高野連も「センバツ改革委員会」を設置するなど課題解決に向けて前身している印象ですが、
「高校野球は教育の一環」と謳う以上、不平等感の解消についてはより一層取り組んでもらいたいと思います。
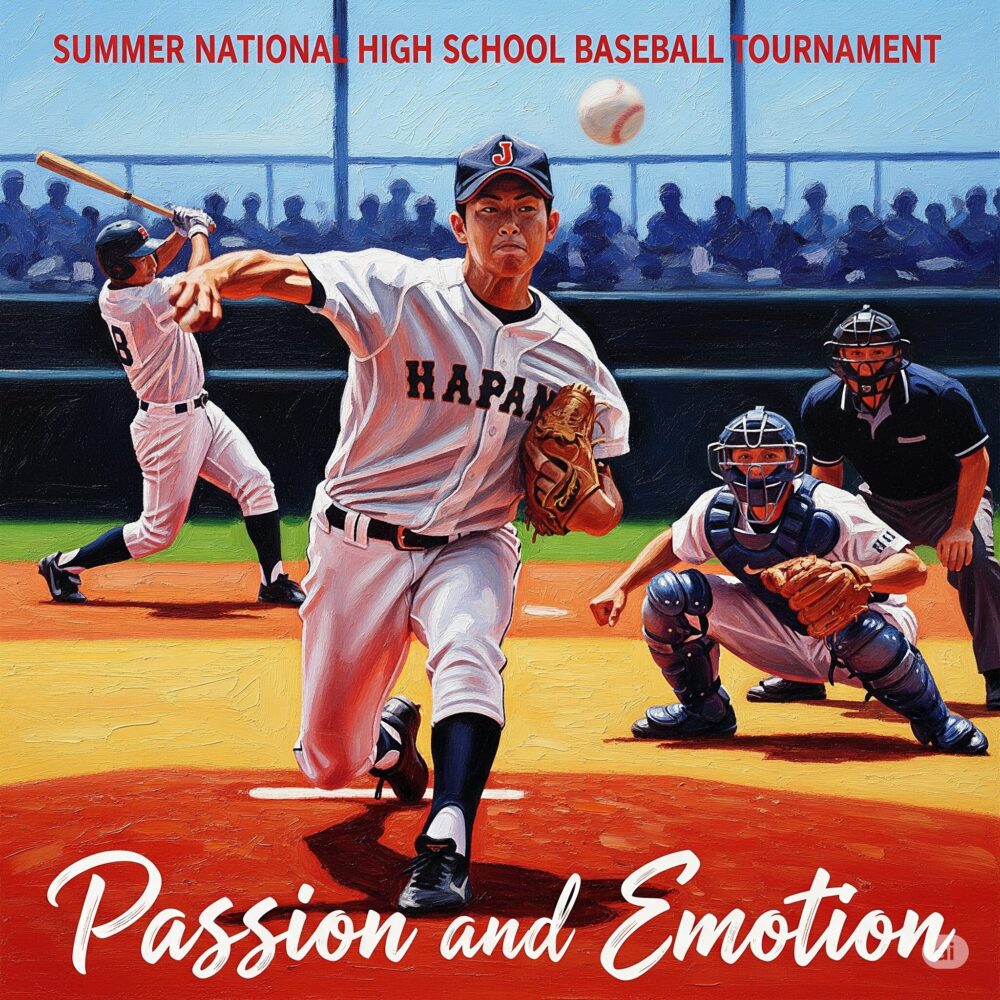


コメント